🪵宮大工が使う伝統技術「継手・仕口」とは?

日本の伝統建築には、
見る人を魅了する美しさと、
何百年も持ちこたえる強さがあります。
その秘密のひとつが「継手(つぎて)」と「仕口(しぐち)」という、
木材同士を組み合わせる技術です。
🔧この記事では、
専門知識がなくてもわかるように、
継手・仕口の基本や目的、
そしてどのように使われているのかを、
丁寧に解説していきます。
🌳そもそも「継手」と「仕口」って何?
木と木をつなぐときに、
ただ接着剤や釘を使うだけではありません。
昔から宮大工たちは、
木そのものの形を工夫して組み合わせてきました。
その方法には2つの大きな分類があります:
- 🪚 継手(つぎて):長さを伸ばすために木と木をつなぐ方法

- 🔨 仕口(しぐち):角度を変えて木と木を接合する方法(L字やT字など)
どちらも、
釘やボルトを使わずに、

木材をしっかりと組み合わせるのが特徴です。
📏なぜ釘を使わないの?
「わざわざ難しい形にするくらいなら、
釘を打ったほうが早いのでは?」
そう思う方もいるかもしれません。
ですが、
木は呼吸する素材。
湿気や乾燥によって伸び縮みする性質があります。
釘を打つと、
その動きに逆らってしまい、
割れたり、
外れたりする原因になることも。
そのため、
木と木が自然に馴染むよう、
力を逃がしながらつなぐ継手・仕口の技術が生まれたのです。
また、
美しさや神聖さが求められる神社やお寺では、
金属を使わずに木だけで作ることが大切とされてきました。
🧩代表的な継手と仕口の種類
継手の例:
- 🪵 腰掛け鎌継ぎ(こしかけかまつぎ):家具にも使われる、
美しさと強度のバランスが良い継手
引用元::kabekoroの楽園
引用元
- 🔷 金輪継ぎ(かなわつぎ):強度が高く、
梁(はり)などの接合に使われます。
引用元:大工の学校
仕口の例:
- 📐 大入蟻掛(おおいれありがけ):T字型に交わる木材に使われます。
引用元:大工の学校
- 🪚 相欠き仕口(あいがきしぐち):簡易的な仕口で、
木の一部を削ってはめ合わせます。
引用元:ナル工房の日々
これらは、
どれも“見えない工夫”が詰まった高度な技術。
🪵木が組み合わさる部分をよく見ると、
芸術的な美しささえ感じられるでしょう。
🧠どうやって作っているの?

継手・仕口は、
図面を描く段階から設計されています。
宮大工は、
寸分の狂いも許されない精度で、
木材を削り、
刻み、
組み立てていきます。
そのためには、
以下のようなプロセスが必要です:
- 📝設計(どんな形で組むか)
- 🪓木材の選定(木目や節をチェック)
- ✍️墨付け(切る線や深さを木に記す)
- 🪚加工(ノコギリやノミで彫る)
- 🧱組み立て(試し組み→本組み)
この流れすべてが職人の手作業。
まさに**「技」と「経験」と「勘」**がものを言う世界です。
📱現代でも使われているの?
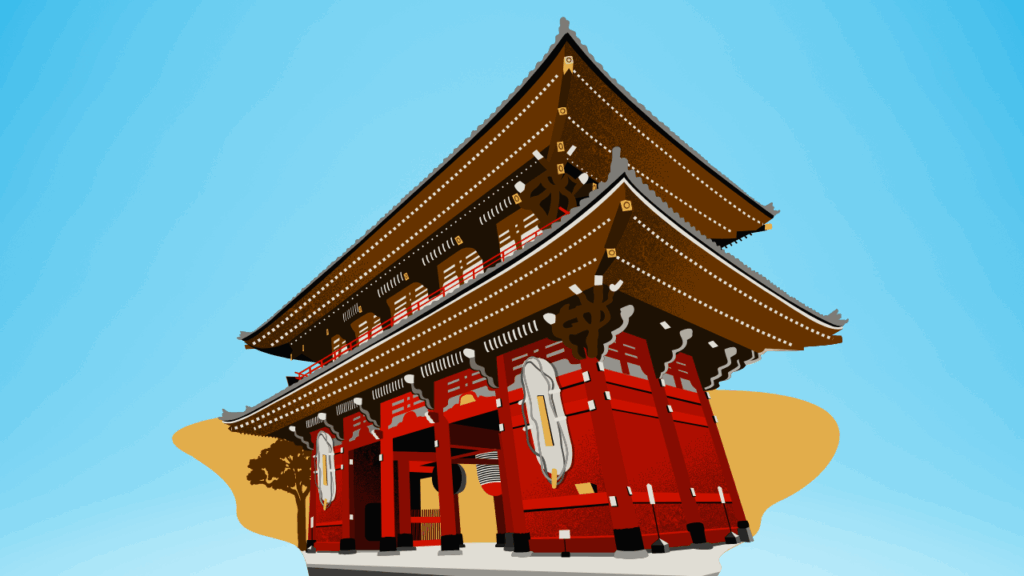
もちろん、
使われています。
特に文化財の修復工事では、
当時と同じ継手・仕口を再現する必要があります。
また、
最近では「伝統技術を現代の住宅に生かす」動きもあり、
🏡木の家づくりや🛖木造店舗の設計にも活かされています。
さらに、
宮大工の技術はSDGsやサステナブル建築の面からも注目されています。
金属に頼らず、
自然の素材だけで強い構造を作るその知恵は、
これからの時代にこそ必要とされています。
✨おわりに
継手・仕口は、
ただの「木をつなぐ技術」ではありません。
そこには、
自然を尊び、
人と建物が共に長く生きるための哲学があります。
普段は目に見えない部分だからこそ、
その価値に気づいたときの感動もひとしお。
ぜひ、
お寺や神社に足を運んだときは、
柱のつながりや梁の交差にも目を向けてみてください。
🔎あなたの目の前に、
千年の知恵と技が隠れているかもしれません。




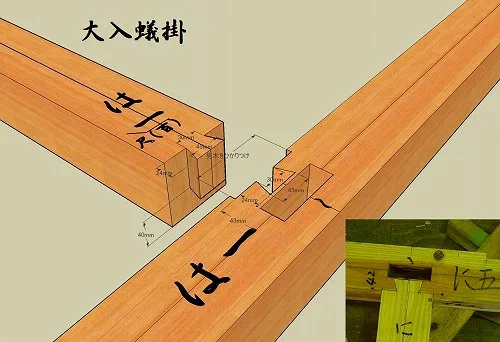
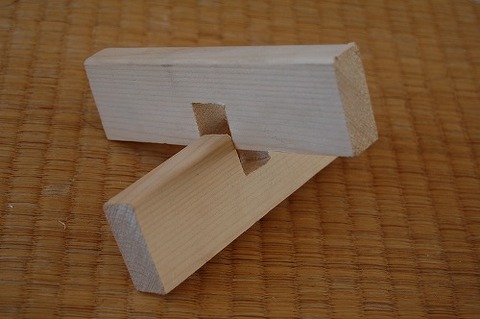
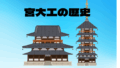

コメント